第8回 新規ビジネス研究会(リアル+オンライン_ハイブリッド形式) – 2025年7月12日(土)
研究会後のレポート
→ レポート – 第8回 新規ビジネス研究会(リアル+オンライン_ハイブリッド形式) – 2025年7月12日(土)
開催にあたって
当会の第8回新規ビジネス研究会を、来たる2025年7月12日(土)にて開催いたします。
今回も前回までと同様、「新しい知識やノウハウに触れる機会を設け、会員ビジネスの発展に貢献する。」ことを趣旨としております。趣旨にご賛同いただき、代々木会のメンバーにとって貴重なFace to Faceの交流の場ですので、ぜひご参加いただければと存じます。
なお、当研究会は効果や成果の共有を目的としております故、一部の内容は会員間のみならず、同伴者、当会のWebサイトなどで共有・公開させていただきます。よって、質疑応答時においては、可能な限り情報公開可能な内容としていただけますようお願い申し上げます。
会長 小貫 智太郎
理事/当研究会幹事 瀧川 淳
開催概要
2025年7月12日 土曜日 14時00分 〜 17時10分頃
ビジョンセンター新橋 (東京都千代田区内幸町1-5-2 平和ビル16階) → 地図(Googleマップ)
13時30分 開場
14時00分 会長あいさつ、幹事から講師紹介など
14時05分 菊池 尚人氏「日本政府のAI戦略(仮題)」
15時05分 瀧川 淳「採択企業による『総務省/偽・誤情報対策技術の開発・実証と社会実装』について報告(仮題)」
16時05分 花光 宣尚氏「AIの最新動向(仮題)」
17時10分 閉会 (閉会後に別会場にて懇親会を予定しております)
*発表者それぞれ、30分発表+20分質疑応答とさせていただきます
講師紹介
菊池 尚人氏
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 特任教授/一般社団法人 CiP協議会 専務理事
1993年慶應義塾大学経済学部卒業後、郵政省入省。国土庁などを経て通信政策局課長補佐にて退官。フランス・パリ高等商科大学プログラム修了。現在、上記のほか、デジタル政策財団 理事、情報通信学会 常務理事、国際公共経済学会 学会理事、東日本大震災アーカイブ福島協議会 会長、超教育協会 常務理事、デジタルサイネージコンソーシアム 評議員などを兼務。
花光 宣尚氏
Enhance Experience Inc. / Synesthesia Lab, Synesthesia Tech Lead/慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media 特任助教
専門は『ふれあいを主体とする技術、体験、価値づくり』。触覚表現やバーチャルリアリティ(VR)、ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)を活用した身体感覚(視覚・聴覚・触覚)体験デザイン、ふれあいを起点とする人・モノ・コトの関係性(身体論)を主な研究領域とする。
瀧川 淳
当会理事/西河技術経営塾 3期修了生/エヴィクサー株式会社 代表取締役社長CEO
2004年に韓国ITスタートアップの日本現地法人としてエヴィクサーを設立し現職。2005年にMBO。2008年以降、音響のディープテックとして、他社に先駆けて自動コンテンツ認識(ACR)技術、音響通信技術を開発。テレビ、映画、舞台、防災などの分野へ応用し、「スマホアプリを使ったバリアフリー上映」「字幕メガネ」を定着させる。2024年から総務省「インターネット上の偽・誤情報対策技術の開発・実証事業」に採択、生成AIのラベリングやディープフェイク対策に取り組む。1979年生。一橋大商卒、奈良県出身。
参加資格について
西河塾代々木会の会員限定の研究会となります。会員外の同伴者の聴講を希望される会員の方は、幹事までご相談ください。上記参加資格のある方は研究会の参加費は無料です。
西河塾代々木会メニュー
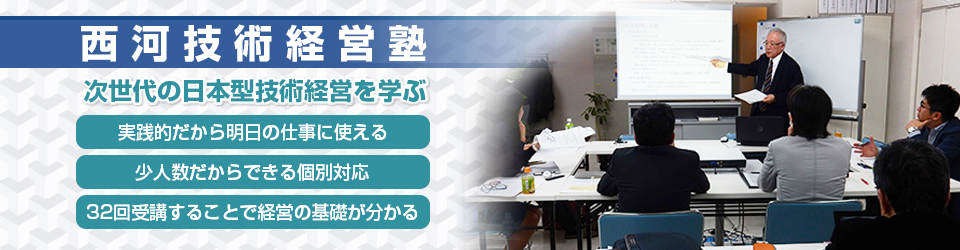 西河塾代々木会とは
西河塾代々木会とは
西河塾代々木会は、西河技術経営塾の修了生および講師による同窓会組織で、一般社団法人アーネスト育成財団運営の西河技術経営塾修了生と同塾の講師による親睦を図ること、および財団運営を後方から支援することを目的として設立されました。
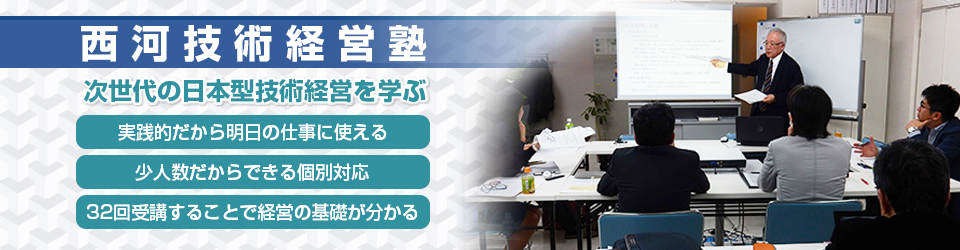
西河塾代々木会は、西河技術経営塾の修了生および講師による同窓会組織で、一般社団法人アーネスト育成財団運営の西河技術経営塾修了生と同塾の講師による親睦を図ること、および財団運営を後方から支援することを目的として設立されました。
